
秋田県ミニ独立国
マレーシアと国際交流
❖1988年(昭和63年)
<下記、秋田さきがけ新聞 1988年7月21日の記事より抜粋>
雄勝郡雄勝町のミニ独立国「小町の国」(佐藤芳嗣総理大臣、会員45人)では、9月にマレーシアの農業青年十人を迎え、町内の農家にホームステイを引き受けてもらって国際交流をする。会員たちも、協力する農家も外国人を受け入れるのは初体験とあって、今から風俗、習慣やマレー語を勉強するなど準備に追われている。
マレーシアの青年たちは、外務省・国際協力事業団の「21世紀のための友情計画」事業で招かれる。受け入れ窓口は、青年協力隊秋田県OB会。県南支部長が「小町の国」副総理の渡部光哉さん=写真店経営=であることから、ホームステイを引き受けることになった。
「小町の国」では、一昨年11月の結成以来、同町が生まれた在所とされる平安時代の歌人、小野小町の知名度を活用して地域興しに努めている。その最終目標の一つに、小町と並ぶ"世界三大美人"クレオパトラ、楊貴妃の誕生の地との交流を掲げており、国際親善の体験を重ねることは会員たちにとって願ってもないこと。本年度の目玉事業として行うことにした。
具体的に動き出したのは今春から。農業青年を泊めるにはやはり農家が最適―とホームステイ先を探したところ、兼業農家含めて10戸確保でき、1軒に1人ずつ泊められることになった。しかし、各農家とも初めての体験とあって不安を伴う。そこで企画されたのが勉強会。これまで会員たちが暇を見つけてマレーシアに関する資料を収集する一方で、民泊先の人たちを集めて学習会を月1回の割合で開いている。
計画では、一行は9月3日に秋田市に着き、翌4日に雄勝町に入る。この日は高橋源蔵町長らも出席する歓迎会に臨んだ後、各農家に泊まる。滞在期間は8日までの4泊5日で、その間、会員たちが町当局の協力を得て町内の地熱利用ウナギ養殖場、リンゴ園、シイタケ栽培施設などを見て回る。また、小学校の授業風景なども見学してもらい、PTAとの交流も計画している。
佐藤総理は「これからは、若者がけん引き役になって地方の国際化を進めたい」と意気盛んだ。
<下記、秋田さきがけ新聞 1988年9月4日の記事より抜粋>
「ようこそ」小町娘が出迎え 雄勝町などでホームステイ
マレーシアから20人来県 国際協力事業団「21世紀のための友情計画」
国際事業団の「21世紀のための友情計画」に基づき、マレーシアの青年20人が3日来県し、JR秋田駅で雄勝郡雄勝町の小町娘5人の出迎えを受けた。一行は同町や北秋田郡鷹巣町、合川町にホームステイし、交流を深める。
同計画は今年で5年目。日本とアジアや太平洋諸国との友好協力を深めるため、各国の青年を招待して、相互理解を深めるのが目的。本県には昨年がシンガポールの教員、一昨年はアセアン諸国の公務員が訪れている。
この日訪れた20人は、マレーシアの農業従事者や農業関係公務員、同団体職員らで、27歳から35歳の男性14人、女性6人。一行は三町に分かれて、農業などにホームステイする。昨年までは2泊3日だったが、海外研修生にとってホームステイが最も印象的だったことから、今回は4泊5日に延ばした。
秋田駅では、雄勝町の加藤幸子さんら5人の小町娘が出迎えた。5人うち3人は秋田市で開かれている東北むらおこし物産展の手伝いに訪れており、この日の歓迎に花を添えた。列車から降りたマレーシア青年らは予想外の歓迎に驚き、小町娘らと握手。一行のリーダーのチェ・ムスタファール・ムダさん=農業省農業担当官=は「秋田の女性は美しいと聞いていたがその通りだ。日本の生活様式や農業を知るとともに、マレーシアの文化や伝統など国全体の事も秋田の人に知ってもらいたい」と話していた。
一行は各町で町民らと交流を深めるほか、金足農業高校生徒と後継者問題の討議なども計画されている。
<下記、秋田さきがけ新聞 1988年9月10日の記事より抜粋>
"国"を挙げて国際交流
マレーシア青年が民宿 雄勝町の小町の国
マレーシアの青年10人が8日までの5日間、雄勝郡雄勝町の農家にホームステイし、地元の人達と国際交流の輪をひろげた。
訪れたのは、国際協力事業団の「21世紀のための友情計画」事業で招かれた20~30代の男性7人、女性3人。農業省などに勤める公務員らだ。迎えたのは、同町のミニ独立国「小町の国」(佐藤芳嗣総理大臣、会員15人)。受け入れ 窓口となった青年海外協力隊秋田県OB会(会員約四十人)の県南支部長が、小町の国副総理という関係から"国"を挙げて歓迎した。
まず、小町の国主催の歓迎会で、高橋源蔵町長や一般町民らと交歓した青年たちは、1人ずつ分かれて民泊した。各家庭では、浴衣姿で手作りの日本料理を味わうなどのリラックスムード。
日中は、会員たちの案内でシイタケ栽培、地熱を利用したウナギ養殖場、リンゴ園などを視察した。リンゴは自国では栽培されていないとあって特に関心を示し、そっと触ったり、もぎ取りを体験した。院内小、湯ノ岱小も訪問し、マレーシア国旗で出迎えを受けたあと、児童たちと懇談した。
このほか、東山森林公園のロッジで、一緒になってマレーシアの一般料理である魚を使ったカレーライスを半日がかりで作り上げ、民泊先の人たちに振舞った。味は、スパイスが存分に効いていてかなり個性的。一般町民も立ち寄って珍味を楽しんだ。
ホームステイを引き受けた農業はいずれも初体験だったが、これで国際交流に自信を持った様子。マレーシア青年たちも「めんこい」「よぐ来てけだんす」などの秋田弁を覚え、すっかり雄勝町びいきになっていた。

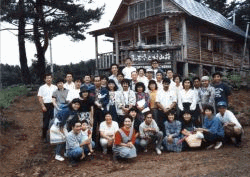

※クリックで拡大